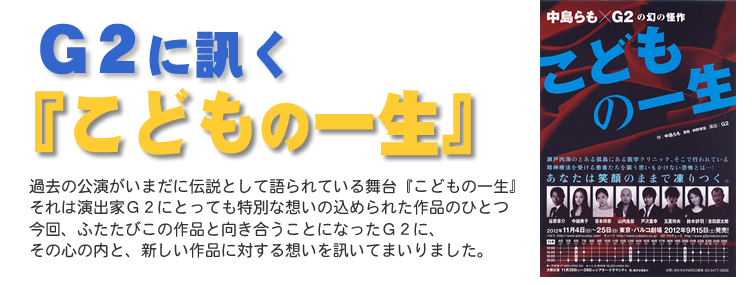
――1990年の初演と1998年のパルコ劇場初進出の当時の意気込みはどんな感じでした?
G2
『こどもの一生』は僕にとっての初めての「ストーリーのある」舞台でした。それまではコント・オムニバスばかりをやっていましたから。
ところがこの前年、別の劇団で普通の演劇を演出させて頂く機会があって、物語というものの強さを実感したんです。それで、当時自分が参加していたユニット「売名行為」でも、コントではなくて「ストーリーのある芝居をやりたい」と思うようになり、台本をお願いするには中島らもさんしかいない、と若気の至りで思い込んでしまったわけです。
そのとき中島氏はアル中で入院中だったのに病室まで押しかけて執筆依頼しました。それくらいの意気込みでしたね。
パルコ劇場は、自分が職業演劇人へ転身するキッカケとなった公演になりました。
だから意気込み、というよりも「気負い」が大きかった。商業的なルールを身につけたい、という思いばかり空回りして。
なんだか無駄というか無理というか、プロたちからすれば無用の試行錯誤も多かったと思います。
ところがこの前年、別の劇団で普通の演劇を演出させて頂く機会があって、物語というものの強さを実感したんです。それで、当時自分が参加していたユニット「売名行為」でも、コントではなくて「ストーリーのある芝居をやりたい」と思うようになり、台本をお願いするには中島らもさんしかいない、と若気の至りで思い込んでしまったわけです。
そのとき中島氏はアル中で入院中だったのに病室まで押しかけて執筆依頼しました。それくらいの意気込みでしたね。
パルコ劇場は、自分が職業演劇人へ転身するキッカケとなった公演になりました。
だから意気込み、というよりも「気負い」が大きかった。商業的なルールを身につけたい、という思いばかり空回りして。
なんだか無駄というか無理というか、プロたちからすれば無用の試行錯誤も多かったと思います。
――その東京公演での衝撃は、いまでもときどき、ご覧になった役者さんから話を聞くことがあります。
当時の反響は実際どんなものだったんですか?
当時の反響は実際どんなものだったんですか?
G2
演出面での「空転」感とは真逆で、いざ幕をあけると相当な反響でしたね。まだマスコミではブレイク直前の古田新太や生瀬勝久、升毅ら、小劇場界のスターも集結していましたし、まずもって中島氏の台本の骨子が素晴らしい。若い作家に潤色してもらってその時代に合うようにしてもらっていたとはいえ、あの着想は並々ならぬものがありましたからね。客席には笑いと恐怖が同時に押し寄せるという、前代未聞の現象が起きていましたし。また、地方公演も盛況で、各地方の劇場やプロモーターの人たちは「この公演は何故こんなに人が入るのですか?」と不思議がっていました。
――初演から22年たったいま、再演する意義というか、現代でも色あせないこの作品の魅力はなんでしょう?
G2
再演する意義ですか? それを今言えたなら苦労しません。それを探しながらお稽古をすることになるでしょう。
 実は、このお話をパルコのプロデューサーから頂いたとき、私は躊躇したのです。それは自分は前回のパルコの公演で『こどもの一生』から卒業した気分でいたからです。
実は、このお話をパルコのプロデューサーから頂いたとき、私は躊躇したのです。それは自分は前回のパルコの公演で『こどもの一生』から卒業した気分でいたからです。
『こどもの一生』の初演以来、他の演目を公演しても色々な方から「『こどもの一生』みたいなのをまたやってください」と言われ続けた日々がありました。そんな状態から卒業したいという想いを込めて作ったのがパルコ版であり、それ以来、別の路線を歩み続けてきました。正直、まさかもう一度この作品に向き合うことなんてあるとは思いませんでした。
再演依頼を受けたとき「それを作るのは難しいな」と思いました。が、「難しい事なのであれば、挑戦すべきではないか?」と発想を変えると、いま自分がやるべき仕事に思えてきたのです。
だから、22年前とは違う、成熟した演出家の腕前を見せてやろう、という挑戦ですね、これは。しかも最新の自分を見せたいし、自分でもそれを試したい。だから、具体的な演出プランは、稽古の1ヶ月前から立て始めるつもりです。
かといって何もやらずに手をこまねいているわけではなく、今はこの20年間で、人間の精神に対する医療が大きく変わっていますので、それをコツコツ勉強しています。初演の時には、診療内科なんて存在しませんでしたし、テクノストレス、ヴァーチャル・リアリティーという言葉が誕生したばかりの時代でした。今は遺伝子レヴェル、分子レヴェルで、心の病気のことが解明され始めています。そういう時代にフィットした感性を身につけた作品として再生したい、という気持ちは大きいですね。
またヴァーチャルでいうと、3D映画の時代。ここまで仮想現実が現実そっくりになるとは、あの頃は思いもよらず、ただのSFでしかありませんでした。その逆に今は、現実に「現実味」を感じることができなくなってきている時代と言えるでしょうね。電車の中で揺られている人のほぼ全員がちっちゃな液晶画面に目を落としているビジュアルは、20年前には想像すらできなかった。なんだか、そういう感覚も作品には反映させたい。コンテンポラリーダンスや、映像などを豊富に使った演出にしたいとは考えています。
が、まだまだ具体的には考えていない。ひとつには只今、台本を改修工事中である、という事情もありますが。
 実は、このお話をパルコのプロデューサーから頂いたとき、私は躊躇したのです。それは自分は前回のパルコの公演で『こどもの一生』から卒業した気分でいたからです。
実は、このお話をパルコのプロデューサーから頂いたとき、私は躊躇したのです。それは自分は前回のパルコの公演で『こどもの一生』から卒業した気分でいたからです。『こどもの一生』の初演以来、他の演目を公演しても色々な方から「『こどもの一生』みたいなのをまたやってください」と言われ続けた日々がありました。そんな状態から卒業したいという想いを込めて作ったのがパルコ版であり、それ以来、別の路線を歩み続けてきました。正直、まさかもう一度この作品に向き合うことなんてあるとは思いませんでした。
再演依頼を受けたとき「それを作るのは難しいな」と思いました。が、「難しい事なのであれば、挑戦すべきではないか?」と発想を変えると、いま自分がやるべき仕事に思えてきたのです。
だから、22年前とは違う、成熟した演出家の腕前を見せてやろう、という挑戦ですね、これは。しかも最新の自分を見せたいし、自分でもそれを試したい。だから、具体的な演出プランは、稽古の1ヶ月前から立て始めるつもりです。
かといって何もやらずに手をこまねいているわけではなく、今はこの20年間で、人間の精神に対する医療が大きく変わっていますので、それをコツコツ勉強しています。初演の時には、診療内科なんて存在しませんでしたし、テクノストレス、ヴァーチャル・リアリティーという言葉が誕生したばかりの時代でした。今は遺伝子レヴェル、分子レヴェルで、心の病気のことが解明され始めています。そういう時代にフィットした感性を身につけた作品として再生したい、という気持ちは大きいですね。
またヴァーチャルでいうと、3D映画の時代。ここまで仮想現実が現実そっくりになるとは、あの頃は思いもよらず、ただのSFでしかありませんでした。その逆に今は、現実に「現実味」を感じることができなくなってきている時代と言えるでしょうね。電車の中で揺られている人のほぼ全員がちっちゃな液晶画面に目を落としているビジュアルは、20年前には想像すらできなかった。なんだか、そういう感覚も作品には反映させたい。コンテンポラリーダンスや、映像などを豊富に使った演出にしたいとは考えています。
が、まだまだ具体的には考えていない。ひとつには只今、台本を改修工事中である、という事情もありますが。