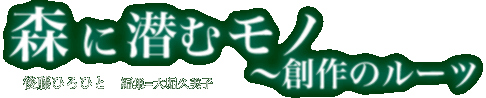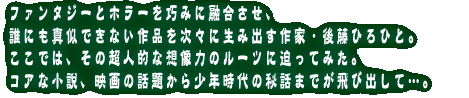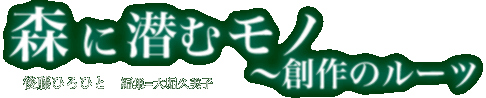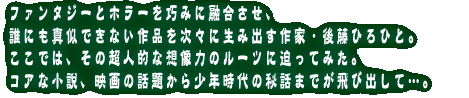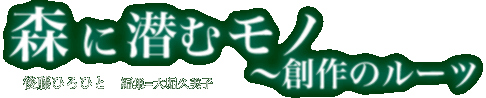
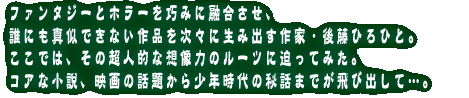
※このインタビューは2002年の『ダブリンと鐘つきカビ人間』の
公演パンフレットに収録されたインタビューの再録です。
「森」、これまで自分で書いたホンの中にも随分登場させましたね。ただ振り返ると、どれも西洋的な森だった。何だろう、日本には森ってないような気がするんだな、この国面積が狭いから。平地に木が生えてたら、伐って家とか建てようとするでしょう「勿体ない」って感じで。「森の定義」というのが正確にどんなものかは分からないけど、考えるに”平地に果てが見えないほどみっしり木が生えてる”所。昼間でも鬱蒼として薄暗く、だから何物かが潜んでいる気配も感じられるっていう。そこにたまらなく想像力を掻き立てられる。でも日本には、それだけの広さと深さを持っている森はほとんど存在しないはず。さっき言った面積や地形上の理由で。傾斜に木が生えていたらそれは「山」だし。
日本が自然と溶け込むように文明を築いてきた国なら(今は違うけど)、西欧は自然を征服して文明を築いたってよく言われるけど、それぞれの森と、そこに潜むモノのイメージを見るとそれがすごくはっきり現れていると思う。
西欧の森は自然を征服のために進攻して来る奴ら、入って来る者をとにかく脅かす、入れるまい・通すまいとする。だからそこに潜むモノ、フリークスや妖精とか神様だったりもするけど、それらは人間を阻む存在として描かれる場合が多い。”世界を閉じておく”ために機能しているんじゃないかな。自然の神秘や怖さを人間に伝えるための装置、とも考えられるね。日本の妖怪なんかは、日常の中の不都合やヤな事を自然のせいにするところから生まれているでしょう。例えばいつも同じ場所で頭をぶつけると「ここには何かいる。きっと妖怪アタマウチだ!」みたいな、そんなんいないけど(笑)。なんか庶民的でスケール感が乏しいよね。戦って克服する対象じゃない。
西欧的発送の、その”阻むためだけに存在するもの”っていうのが作家の目から見ると楽しくてしょうがない。制限があるっていうことは、逆にいうと、それを克服すれば望んだ場所に行けたり、願いがかなえられたりするわけで、それはものすごくドラマティック。障害を作って、キャラクタ−にいかに突破させるかを考える。森やら海やら、自分の書いた芝居の中で作った、行く手を阻むあらゆる障害を分析したら、それだけで1冊本が書けるなって昨日思ったんだ(笑)。
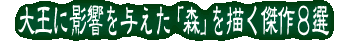
僕の中に「森」のイメージの土台を作ったのは、やっぱり欧米の小説とか映画でしょうね。そう、まずはルイス・キャロル。2作あるうちの『鏡の国のアリス』のほうが、森を旅する割合が高いんだけど、そこでアリスの行く手を阻むキャラに”トウィードルダムとトウィードルディー”って双子がいて。森の中に2人並んで身動きひとつせずに立っている。アリスが人形かと思って近づくと、「俺たちを蝋人形だと思ったな! だとしたら見物料を払え。そうじゃないなら口をきくべきだ」みたいな理屈をこねたり、詩を暗唱してアリスの足を止める。何のために立ってるのか、なんて説明はなしでね。もっと傑作なのが、これはキャロルの詩なんだけど「スナーク狩り」。ベルマン(鐘鳴らし役!)を隊長にブッチャー(肉屋)、バンカー(銀行家)などBで始まる職業の男たちが、災いをもたらす怪物「スナーク」狩りの旅をする。でも誰もスナークの姿や居場所を知らないんだ。しかも最後は「さよう、スナークは、たしかに、ブージャムだったのです」ってフレーズで、スナークの正体も分からないうえ、新しい別の怪物の名前にすり変わってしまう、何の解決にもなってない(笑)。これが童話として読み継がれているイギリスって国は、やっぱり変わってるね。
ナイジェリアの作家エイモス・チュツオーラの『ブッシュ・オブ・ゴースツ』も奇妙キテレツ。幽鬼(ゴースト)のいるジャングルを旅して行くんだけど、”服を脱がないと渡れない橋”とかが出て来るんだ。同じ森でもジャングルだとやはり空気感が違うのかも知れない、温度とか湿度が高い感じがして。熱帯雨林だからかな。 |